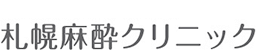医魂商才ノススメー新紙幣発行に思うことー
7月3日に、20年ぶりに新紙幣が発行されます。医師としては、北里柴三郎という偉人が採用されたことは喜ばしいことですが、「諭吉さん」の愛称で一万円札に描かれていた福澤諭吉は日本人の心の開国に貢献した偉人です。「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズ」という有名な一節で始まる『学問のすゝめ』は攘夷に染まっていた混乱期の日本人の心に真の近代化に向けて進むべき道標を示しました。
現在の日本の医療制度は多くの問題を抱えてます。具体的には、患者は誰でも最高の医療を望むが、医療費を負担する立場からすればできるだけ保険料や税が低い水準である事を望みます。しかし、これは100円ショッブでブランド品を求めるようなもので、行政はこの事に対する解答を示してはくれません。全ての責任を負わされるのは医師、医療機関ですが、現場での処理能力は限界を超えており、これらのサービスにどの位の財源が必要なのか、どのように適切に配分していけば良いかは、答えられない状態です。しかし、今までの医学教育は「医は仁術」とし、経営能力は必要ないものとしてきました。これが、今日の医療崩壊の大きな原因の一つです。かつて経営破綻したJALの例を引くまでもなく、親方日の丸の体質があまりにも深く医学界に浸透してきました。医療関係のリーダー達でさえ、その多くは闇雲に医療費の増額を訴えるのみに終始してます。それほどに、医師は経営のスキルを持っていないのです。
それでは、医療は他のサービス業と同じように完全に民間企業に委ねてよいものでしょうか?私は、反対です。それは、民間企業主導では、医療の公平性、平等性が保証されないからです。最低限平等な医療サービスは全国民に保証されなくてはなりません。民間企業が営利のみを追求すると、昨今の投資を巡る企業犯罪のようなモラルハザードを起こします。日本資本主義の父といわれる渋沢栄一は営利主義の弊害を予知し、『論語と算盤』を著し、「道徳経済合一説」という理念を打ち出しました。理想の経営者は片手に論語、片手にソロバンを持つといった高い倫理感が必要であるという理念は、現在にも通用するものです。しかし、医師の場合には、倫理と医療技術といった両立しなくてはならないものが既にあり、その上にさらに経済学,経営学まで理解しなくてはならなくなってきた事が両立を困難にしています。
以上の事から、これからの医療には経済学、経営学が必要となってきますが、医師がこれを全て担う事は難しいです。したがって、SPC(特定目的会社)のような「医経分離」は理にかなっています。しかし、医師以外の経営陣主導による病院経営は医療現場との距離ができ、現場に対する理解不足、さらに、そこに従事する医師達の就労意欲が低下し、長期的には成功しません。最良の解決策は、医師が経営学、経済学の基礎を身につけ、医療現場、事務職両方を巻き込んで、経営のリーダーシップを取っていく事です。制度が違うので一概には比較できないが、米国ではMBAは病院経営に必須の資格になってきており、大学院でもMD/PhDコースと並んで、MD/MBAコースを有する大学が増えてきています。より良い医療を行うためには、経営的手腕が必要です。医は仁術ですが、算術(経営力)も同時に必要なのです。
朝すっきりと起きられますか?−鉄欠乏は、多彩な愁訴と関係−
鉄欠乏性貧血による症状は実に様々です。具体的には、寝起きが悪い、疲れやすい、肩こり、湿疹、頭痛、風邪を引きやすい、髪が抜ける、注意力が低下、イライラ・神経過敏、歯茎から出血、アザ、動悸息切れがする、むくみ、爪が変形、割れやすい、食欲不振、口角口唇炎など、多彩な愁訴に関係しますが、慢性に経過する鉄欠乏は自覚症状に乏しいのが特徴です。
現代ではライフスタイルや環境の変化によって食物からの鉄の摂取量が減少しています。さらに、成長に応じて鉄の需要は増大、過度な運動でも鉄が失われます。女性はさらに、月経血からの喪失、妊娠、分娩で鉄の需要が増加します。子宮筋腫や悪性腫瘍などによる出血量の増加に伴い、需要量が増加します。
病院で処方される鉄剤は非ヘム鉄です。鉄は胃酸により、鉄イオンに変化してから吸収されるので、胃酸の分泌が低下している人はヘム鉄の補給が適しています。
鉄以外にも栄養バランスの乱れは様々な不定愁訴を引き起こし、病気の原因にもなります。血液検査によって、ご自身の体の状態を知り、適切な栄養素の補給を行なうことによって、愁訴の改善だけでなく、身体症状を含めた全身状態の改善も可能になります。
最新の健康医療
健康は極めて大切だということに反対する方はいないでしょう。では、どうやって健康を維持するかは考え方が様々で、まめに健康診断をして早期発見早期治療に努めるという方もいれば、様々な情報を入手して病気の予防に努めるといった方、また、全て運に任せて好きなように人生を謳歌するといった方もいるかもしれません。
高齢化に伴い、我が国でも癌患者が増加しています。しかし、アメリカでは近年、癌による死亡はむしろ減少しており、日本とは逆の現象が起きています。これは、早期発見、早期治療の成果というよりはアメリカでは国民に「予防医学」が広く浸透していることが大いに関係していると思われます。予防医学といってもその方法はいろいろありますが、アメリカでは最近「自然療法医」ND(naturopathic doctor)という資格が認められる州も増えてきており、多くの癌患者などが彼らによる代替医療を受けています。
代替療法とは、厳密には「通常医療の代わりに用いられる医療」をいいますが、単独で病気の完全治療効果を得ることは少なく、実際には通常医療と併用され、統合医療といった形で提供されることが多いです。「人はその人が食べたものでできている」。栄養療法は「医食同源」といわれるように極めて有効性の高い自然療法の一つです。高濃度ビタミンC点滴療法はノーベル化学賞を受賞したポーリング博士が報告して以来、癌に対する代替療法として広く用いられており、近年では、癌以外に様々な慢性疾患の治療に使われています。ビタミンC以外の栄養を効率よく摂取する方法として様々なサプリメントを用いる栄養療法は、「オーソモレキュラー療法」といった形で、カナダの精神科医ホッファー医師によって進められ、精神疾患を薬物を使わずに治療する方法として認められています。(http://www.orthomolecular.jp)
キレーション療法は、動脈硬化をはじめ、様々な血流障害に起因する病気の治療に用いられ、心筋梗塞に対してもバイパス手術を選択しない場合の代替療法として有効性が報告されています。
現代医療が、人類に長寿を当たり前のものとしてくれたことに疑いの余地はありません。しかし、本当に必要な健康寿命の延長にはそれだけでは不十分です。健康寿命の延長には、予防医学に配慮した新たなアプローチが必要と考えます。